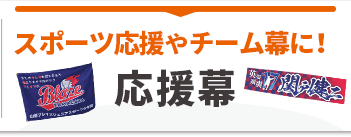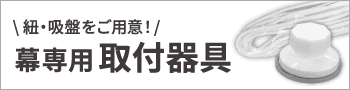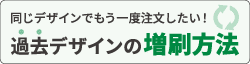紅白幕の意味や使われ方|祝いごとに使われるようになったきっかけは?

このコラムでは、紅白幕の意味や由来、使われている場面、紅白幕に似ている幕などを解説・紹介しています。紅白幕への理解が深まる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
紅白幕の意味と使われ始めた由来
紅白幕の「赤(紅)」と「白」は、日本ではもともと、めでたい・縁起がよい色の組み合わせとして使われる色でした。
紅白の意味は二つあり、「対抗する二つの色」「人生の中でハレの舞台で使われる色」というものです。
対抗する二つの色は、源平合戦で赤と白に分かれて戦った、という言い伝えが由来だとされています。人生の中でハレの舞台で使われる色は、赤が赤ん坊、白が老いや別れに例えられるからだと言われています。
紅白幕に赤ではなく紅という漢字が用いられているのは、赤が「むき出しであること」「裸」といったマイナスのイメージを持つからと言う説があるからです。実際に、「赤裸々」「赤貧」といった熟語が現在でも使われています。
「紅白」という言葉は古くから使われており、紅白幕自体は昭和初期頃から使われ始めたのではないか、とされています。おめでたい場面で「縁起が良い場だ」ということをアピールするために、赤と白の布を飾ったことが紅白幕始まりなのではないかと言われているのです。
紅白幕が使われる場面3選
ここでは、紅白幕が良く使われる場面について、3つ紹介します。
地鎮祭などの安全を願う式

紅白幕は地鎮祭や竣工式など、建物を建てる場面での安全を願う式で使われます。
地鎮祭は、建設工事の前に土地の神様をまつり、工事の無事を祈るために行われるものです。土地を使用することを祝い、安全に建設できるように祈るために紅白幕が使われます。
竣工式は、建物が無事に完成したことを祝うものであり、感謝するために紅白幕が使用されます。
入学式・卒業式などの学校行事

新しい門出や始まりを祝うため、紅白幕は入学式・卒業式などの学校行事でも用いられます。
紅白幕で式場の壁を覆う、というかたちでよく使われています。式典の内容や「おめでとう」というメッセージが書かれた、垂れ幕やパネルも一緒に設置されやすい傾向があります。
お祭りや店舗の感謝イベント

赤と白が使われ遠くからでも目を引きやすい紅白幕は、お祭りのやぐらや店舗のセール会場・感謝イベントなどでも使われています。会場をにぎやかにしたり、華やかになるよう会場を演出したりといった効果が期待できるのです。
紅白幕に似ている縦縞模様の幕を紹介
紅白幕に似ている縦縞模様の幕である、黒白幕・青白幕・定式幕をそれぞれ紹介します。
黒白幕は高貴な雰囲気が特徴


黒白幕は黒と白の縦縞模様の幕で、高貴な雰囲気が特徴です。鯨幕(くじらまく)とも言われており、黒はクジラの皮を、白はクジラの脂肪を表すとされています。
黒と白の配色は葬儀関連で目にすることが多く、実際に告別式で良く見られます。しかし、本来は慶弔に関係なく、冠婚葬祭すべての場面で使えるのです。
青白幕は神聖な場面で使われる


青白幕は青と白の縦縞模様の幕で、浅黄幕(あさぎまく)とも言われます。
神聖な場面で使われ、「勝手に立ち入ってはならない」ことを示す役割があるのです。そのため、皇室の新年祝賀や、地鎮祭で紅白幕と一緒に使われています。
歴史は古く、江戸時代ごろから使用されていたと言われています。
定式幕は歌舞伎で使われる


定式幕は3色の縦縞模様の幕で、歌舞伎で使われています。
良く見かけるのは「黒・萌黄・柿」「黒・白・柿」の3色です。定式幕は、歌舞伎の舞台と客席とを分けるための幕という意味があり、お祝いごとで使われる紅白幕とは異なります。
まとめ
今回のコラムでは、紅白幕の意味や由来、使われている場面、紅白幕に似ている幕などを紹介しました。
古くからの歴史を持つ紅白幕は、現在でも広く使用されています。生地の種類も豊富で、さまざまなシーンで活用できるでしょう。
コラムをきっかけに、紅白幕への理解をぜひ深めてみてはいかがでしょうか。
紅白幕の仕様については、「紅白幕の基礎知識」を解説している記事をご覧ください。