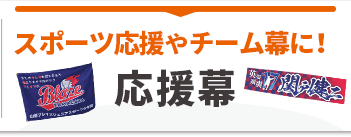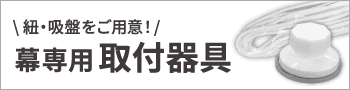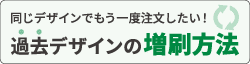浅黄幕(浅葱幕)とはどのような幕?歴史や使われる場面を解説

浅黄幕(浅葱幕)とは、日本古来の浅葱色と白色から構成される縞模様の幕のことです。
その歴史は紅白幕や鯨幕よりも古く、現在でもさまざまな神事で用いられているものの、その意味や役割を知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、浅葱幕(浅葱幕)の特徴や使われる場面に加え、そのほかの歴史ある幕についてもあわせて解説します。
浅葱幕(浅葱幕)への理解が深まる内容となっていますので、興味をお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。
浅黄幕(浅葱幕)とは?浅黄幕の歴史について
浅黄幕(浅葱幕)は、「あさぎまく」と読み、薄い藍色と白色の布を交互にあわせた幕を指します。
江戸時代ごろから使われ、当時染料に使われた植物が淡い緑色(藍色)だったことが、幕の色の由来といわれています。
浅葱幕(浅葱幕)は、神聖な領域を示す目印として主に地鎮祭や上棟式などの神事に使用されるほか、地域によっては仏式や神式の葬儀で使うことも少なくありません。
また、一定の場所を囲い込むという意味から、合戦時には「陣幕」として陣地で使用された歴史もあるようです。
浅黄幕(浅葱幕)が使われる場面
神聖で風格のある浅黄幕(浅葱幕)は、歌舞伎劇や祭事などの装飾として用いられるのが一般的です。
ここからは、浅黄幕(浅葱幕)が使われる場面について詳しく解説します。
歌舞伎の大道具として用いられる
歌舞伎では、浅葱色は空や空間を表現しているといわれ、舞台の光景を一変させるために浅黄幕(浅葱幕)が用いられます。
主な使い方は、吊ってある幕を瞬時に床に落として、舞台を出現させる「振り落とし」や、演技中に天井から幕を落として瞬間的に舞台を覆う「振りかぶせ」といった仕掛けです。
こうした仕掛けは、大道具だけでなく、俳優の姿を一瞬で見せたり隠したりする際にも使われます。
いずれも歌舞伎ならではの技法で、見る人を飽きさせない視覚的な楽しさを演出しています。

祭事などの装飾で用いられる
皇室行事である新年祝賀や園遊会、地鎮祭など祭事の装飾として使われることが多いのも、浅葱幕(浅葱幕)の特徴です。
浅黄幕(浅葱幕)が張られた場所は「立ち入ってはいけない神聖な場所」であり、神と接する場所を示すことから、祭壇周辺を囲うように使われる場合もあります。
なお、地鎮祭は土地の神様に工事の無事を祈願するだけでなく、施主や工事関係者などが良好な関係を築く機会でもあります。行う際は、浅黄幕(浅葱幕)とともに紅白幕も用意しておくと良いでしょう。

浅黄幕(浅葱幕)以外で歴史のある幕
浅黄幕(浅葱幕)のほかにも、歴史ある幕はいくつかあるため、用途に応じて使い分けると良いでしょう。
たとえば、赤色・白色の鮮やかな色彩が特徴の「紅白幕」は、入学式や卒業式、成人式などお祝いの式典で用いられています。
また、黒色・柿色・萌葱色の3色の縦縞が並んだ「定式幕」は歌舞伎や落語などの幕開きや終幕に、白色・黒色の「鯨幕」は葬儀や皇室で行われる納采の儀などに使用されています。
浅黄幕以外の幕に関してはこちらの記事でも紹介しておりますので、参考にしてみてください。
まとめ
浅葱幕(浅葱幕)は、淡い藍色で染められた日本の伝統的な幕の1つです。その歴史は古く、神聖な場所を示す目的で、主に地鎮祭や上棟式といった神事で使用されます。
ほかにも、歌舞伎の舞台効果や地域によっては葬儀一般など、浅葱幕(浅葱幕)はさまざまな場面で活用されています。なお、宗派や地域によって考え方が異なるため、浅葱幕(浅葱幕)が必要な場合は、それぞれの慣習を確認したうえで使用しましょう。