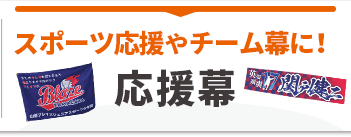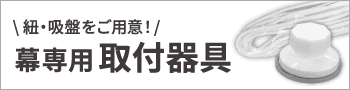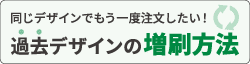神社のぼり旗はどうやって立てる?設置のポイントや意味を解説

神社のぼり旗は神社の風格や伝統を大切にし、信仰心や感謝の意を示す重要な役割を果たしています。通常の販促用のぼり旗とは異なる目的や意味について理解し、その神社にとって適切な旗を制作することが肝要です。
この記事では神社のぼりの意味や特徴に焦点を当て、その立て方やサイズ、デザインなども詳しく解説します。神社のぼり旗を制作して設置する際にぜひお役立てください。
神社のぼり旗は向かい合わせに立てることが多い


神社にあるのぼり旗は通常、参道の左右に向かい合わせに立てられます。この立て方は「対仕立て(にらみ)」と呼ばれ、統一感と神聖な雰囲気を醸し出します。
とくに注意が必要なのが、のぼり旗に取り付けられた「チチ」と呼ばれる白い輪っかです。チチの位置を考慮することで、同じデザインでも左右対称に見えるようにします。
たとえば、のぼり旗の文字が正しく表示されるように、右チチと左チチの位置関係に気を配らなければなりません。風向きや見えやすさを考慮して、右チチと左チチの向きを適切に調整することも細かな気遣いとして必要です。
神社にのぼり旗を立てる際には、対仕立ての配置やチチの位置調整に気を付けながら立てていきましょう。
神社のぼり旗を設置する意味と目的
神社にのぼり旗を設置するのは重要な意味をもちます。ここでは「奉納」「祈願」「神様を招く」という3つの目的に分けて解説します。
奉納の目的

奉納のぼりは個人や企業などの信仰心を示すために制作され、以下のような目的をもって立てられることが多いです。
- 装飾によって威儀を正し、神様への尊敬や信仰心をうながすため
- 神社への奉納金や寄付に対する感謝の意を示すため
- 神社をにぎやかに飾ることで、神様に喜んでもらうため
上記のような目的で設置される奉納のぼりですが、のぼりを制作するには費用がかかります。そのため、氏子や崇敬者が自作で持ち込んだり、神社が氏子や崇敬者からの奉納金を募り、その資金でのぼり旗を制作したりします。
奉納のぼりの上部には「奉納」や「奉献」といった文字が使われ、奉納した人の名前や会社名が記されることが一般的です。神社によって色やデザインが決まっている場合があるため、制作を考える際は事前に神社と相談するようにしましょう。
祈願の目的

祈願のために使われるのぼり旗は、個人や企業の願い事がデザインされたものです。祈願のぼりは、その神社の御神徳を広く知ってもらう役割も果たしています。
御神徳は「商売繁盛」「家内安全」「縁結び」「合格祈願」など、神様に祈願する内容を明確に示すものであり、のぼり旗を立てるのは神社への信仰心を表す一環です。
祈願のぼりには神社の名称や御神徳を表示する以外に、神様をキャラクターにしたり、神社に伝わる神話を描いたデザインが採用されたりする場合があります。祈願のぼりは、単なる願い事を伝える手段に留まりません。神社の歴史や特徴を伝える存在として、神社の雰囲気をより豊かにする役割も果たしています。
神様を招く目的

神社のぼり旗には「大幟(おおのぼり)」があり、別名「招代(おぎしろ)」とも呼ばれます。大幟は神様が神社に降りてくるための目印として使われ、おもに神社の入り口や目立つ場所に立てるのが一般的です。
大幟のなかには10mを超える大きなものもあり、神事の際に重要な役割を果たします。遠くからでもよく目立つように、のぼりの先端に笹竹やスギの葉を付ける神社もあります。
神社のぼり旗に使われるサイズ
奉納のぼりや祈願のぼり、そして大幟として使用される神社のぼり旗には、目的や用途に応じてさまざまなサイズが存在します。以下に種類ごとのサイズを紹介します。
■奉納のぼり

奉納を目的とするのぼり旗は、横600mm×縦1,800mmのサイズが一般的です。参道に数多く並べることを想定している場合は、横幅450mmのスリムなのぼり旗が使用される場合もあります。
■祈願のぼり

個人や企業の祈願や御神徳を示す神社のぼり旗は、奉納のぼりと同じように横600mm×縦1,800mmのものが主流となっています。
■大幟

大幟は奉納のぼりや祈願のぼりとは異なるサイズで作られるケースがあります。たとえば、横500mm×縦2,700mmサイズのものから7m超えのものまでさまざまです。大幟は神様が迷うことなく降りてくださるように願って作られているため、通常よりも大きくなる傾向があります。
※弊社で取り扱っているのぼり旗の最大サイズは、横900mm×縦2,700mmです。大幟のサイズや特注サイズは取り扱っておりませんのでご了承ください。
以上のサイズはあくまでも目安であり、神社や地域によって異なります。その神社の特徴や目的に応じて適切なサイズを選ぶことが大切です。
さらに、のぼり旗を立てるにはポールが必要です。通常、注水式のスタンド(中に水を入れて重りにするタイプの土台)を使用して固定します。あるいは階段の柵にくくりつけたり、大幟の場合はポールを埋めて固定したりする場合があります。
のぼり旗を立てる際は、のぼりのサイズに適したポールや土台を選定することが肝要です。
神社のぼり旗に使われる生地
広告宣伝用ののぼり旗は、軽くて扱いやすいポリエステル生地が好まれますが、神社ののぼり旗では丈夫で耐久性が高い綿生地が主流です。
綿生地の種類については以下のようなものがあります。
- 金巾(かなきん):たて糸とよこ糸を交互に交差して作られる平織の生地
- 天竺(てんじく):金巾よりも厚手の平織の生地
- 葛城(かつらぎ):斜めの模様が見られる綾織の生地
- 帆布(はんぷ):船の帆布に使われているような厚手の生地
- 舞布(まいふ):のれんに使われるような、ざっくりとした風合いの少し厚手の生地
上記の種類は、のぼり旗の制作会社によって異なりますので、事前に確認しましょう。
※弊社では綿素材ののぼりは取り扱っておりませんのでご了承ください。
神社のぼり旗は神聖なものであり、その風格や伝統を重視しつつ、耐久性も求められます。風雨に強い綿生地の採用は破れにくく、神聖な場を守ることにつながります。のぼりを制作する際は、より丈夫な綿生地を選ぶとよいでしょう。
神社のぼり旗のデザイン例




神社のぼり旗は、奉納や祈願の目的によって異なるデザインが採用されています。
奉納のぼりの布地には青や紺、紫、緑、黄などが使われ、文字の色は白や黒、赤が一般的です。デザインはシンプルであり、「奉納」や「奉献」の文字や氏名や企業名を書く箇所があります。大幟も同様に、神社によって赤地に白字、白地に黒字など異なりますが、その多くは2色印刷です。
祈願のぼり旗の基本色は赤と白の2色であり、とくに魔除けの色とされる赤は神社のぼり旗によく用いられます。のぼりには祈願の内容をはじめ、神社や神様の名称が記されます。
のぼり旗の書体については制作会社によって異なるため、あらかじめ確認してみましょう。たとえば大幟には太楷書体、小幟では江戸文字なども使われます。書体デザインによって印象が変わるため、神社の雰囲気に沿う字形を選ぶことが重要です。
まとめ
神社ののぼり旗は奉納や祈願、神様の招来のために制作され、神社を装飾し、威儀を正すことで畏敬や感謝の意を表現するとされています。神社にのぼり旗を納める際は、神社の御神徳や雰囲気に合うデザインを検討することが不可欠です。また、用途や特徴に応じて適切なサイズを選定し、配置や立て方に留意しましょう。
不明点や疑問が生じた場合は、あらかじめ神社と相談することも重要なポイントです。この記事で紹介した内容を参考にして、信仰心や祈願の気持ちを心から示せるようなのぼり旗を制作しましょう。